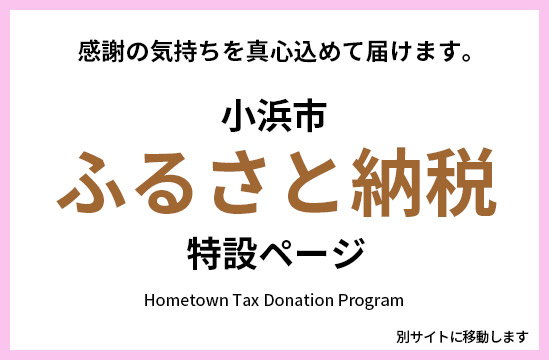◆所在地◆
小浜市岡津44号塩汲場
◆アクセス◆
JR加斗駅より1Km
◆概要◆
小浜市街地から国道27号線を西へ約10キロメートルのところ、小浜湾の奥まった位置に遺跡は所在します。青戸の入江に面し、万葉集の歌枕にも詠まれている若狭富士と称せられる青葉山が真正面に写し出される風光明媚な所にあります。
本遺跡は昭和53年と昭和54年に発掘調査を実施しました。若狭地方には、土器製塩遺跡が50ヶ所確認されていますが、本遺跡はそれらの中でも、極めて保存の良好なものとして、香川県の喜兵衛島の製塩遺跡と共に国の史跡に指定されました(指定範囲4,981平方メートル)。
本遺跡は、古墳時代後期から奈良時代にかけてのもので、若狭の製塩土器の編年からは、浜禰2B式・岡津式・船岡式のそれぞれの時期に属します。石を敷きつめた製塩炉跡は、岡津式(1号炉から4号炉)、船岡式(5号炉から9号炉)の合計9基検出している。さらに現海岸線より約20メートル奥に海岸部遺構(護岸)、その東に南北約30メートル、東西約10メートルの範囲の性格不明の焼土面が検出されています。古代の土器製塩工房跡の全容を示す遺跡といえます。
若狭で生産された塩は、奈良の都へ税(調塩)として納められていた。このことは藤原宮や平城宮出土の若狭からの送り状(木簡)がそれを物語っています。
若狭の東部、三方町食見の近世の里謡に「嫁にやるまい海辺の村へ 夏は塩垂れ 冬は苧の根を叩く」とうたわれていることから、土器製塩の労苦や、重税にあえぐ古代の若狭人の姿がうかがえます。
このページに関するお問い合わせ先
文化観光課
- 電話番号0770-64-6034
- ファックス
- お問い合わせ