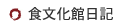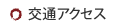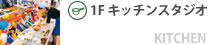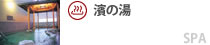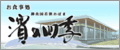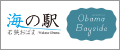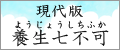ご利用案内
インフォメーション
 食文化館は、小浜市内の情報を発信する機能も持ち合わせています。
食文化館は、小浜市内の情報を発信する機能も持ち合わせています。自分で目的地をカスタマイズして散策マップを作る「My Obama Promenade」と、最新情報をダイレクトにお知らせする「若狭おばまの旬情報」などを設置しています。
散策マップは印刷してお渡しできますので、観光に役立てるもよし、遠方の知人に小浜を紹介するツールとして使うのもおすすめです。
ミュージアム
 外国人観光客が日本にくることの目的第一位は「本場の『すし』を食べること」だそうです。その「すし」のルーツと、日本食の美味しさの秘密を紹介する「世界で愛される日本食の代表『すし』」のブースを始め、多くのテーマを扱った展示を行っています。
外国人観光客が日本にくることの目的第一位は「本場の『すし』を食べること」だそうです。その「すし」のルーツと、日本食の美味しさの秘密を紹介する「世界で愛される日本食の代表『すし』」のブースを始め、多くのテーマを扱った展示を行っています。年のはじめに一年の無事を願って食す「日本の正月食の象徴『雑煮』」、民俗の宝庫である若狭おばまの一年を食で紹介する「囲みかたらう伝統行事と食」、ユネスコ無形文化遺産の「和食」、日本遺産の「御食国若狭と鯖街道」などを多くの再現料理レプリカとともに紹介しています。
| 開館日時 | 9:00〜18:00(3/1〜10/31) 9:00〜17:00(11/1〜2/末) |
| 休館日 |
水曜日(祝日の場合は開館します) 年末年始(12/28〜1/5) |
| 料 金 | 無料 |
キッチンスタジオ
 若狭の新鮮な食材を使った調理体験・加工体験又は、食育に関する講演会などができます。ここは、生涯食育の活動拠点施設として位置付けており、子どもからお年寄りまで、幅広いニーズに応えられる食の提案を行っています。
若狭の新鮮な食材を使った調理体験・加工体験又は、食育に関する講演会などができます。ここは、生涯食育の活動拠点施設として位置付けており、子どもからお年寄りまで、幅広いニーズに応えられる食の提案を行っています。キッズ・キッチンとキッズイベントのご予約・お問い合わせ
現在ご予約は、お電話でのみお申し込みを受け付けております。 御食国若狭おばま食文化館 TEL:0770ー53ー1000 FAX:0770ー53ー1036
調理体験 ※要予約
 小浜の豊富な食材を使い、団体・グループ等で季節の料理を楽しく作ることが出来ます。小浜市の食生活改善推進員の有志で構成するグループマーメイドが指導にあたります。おいしい昼食・夕食としてご利用下さい。(4名様以上でお申し込み下さい。)
小浜の豊富な食材を使い、団体・グループ等で季節の料理を楽しく作ることが出来ます。小浜市の食生活改善推進員の有志で構成するグループマーメイドが指導にあたります。おいしい昼食・夕食としてご利用下さい。(4名様以上でお申し込み下さい。)| 【調理体験で使用する食材について】 | |
| 食材は基本的に地元のものを使用します。生産していないものは国産のものを使用いたします。 | |
| 料 金 | 1,000円〜/お一人様 |
| 利用時間(目安) | 10:00〜13:00 14:00〜17:00 18:00〜21:00 |
| そ の 他 | ※ 月ごとに体験内容が変わります。 ※ ご希望により体験内容の変更が可能です。 お気軽にご相談下さい。 ※ その他・詳細についてはご相談下さい。 |
加工体験(おみやげ作り) ※要予約
小浜の代表的なおみやげが作れます。小浜市の食生活改善推進員の有志で構成するグループマーメイドが指導にあたります。家族や友人へのおみやげ作りにチャレンジしませんか?
| 料 金 | 600円〜1,900円 |
| 利用時間(目安) | 10:00〜21:00(所要時間約1時間〜2時間程度) |
| そ の 他 |
※ 体験内容によって、料金・時間帯が変わります。 ※ その他・詳細についてはご相談下さい。 |
>>
体験メニュー(PDF)
貸し調理台 ※要予約
材料・調味料等を持ち込んで、自由に調理体験が出来ます。グループやサークルでご利用下さい。(調理台および調理器具のみの貸出しとなります。)
| 料 金 | 500円/1台(3時間) ※冷暖房を使用する場合は別途料金が必要です。 |
| 利用時間(目安) | 10:00〜13:00 14:00〜17:00 18:00〜21:00 |
| そ の 他 | ※ 材料、調味料は各自でご用意下さい。 ※下記の事項にご留意下さい。
|
キッチン用品
キッチンスタジオでは、たくさんの備品をご用意しております。
さまざまな調理にご利用下さい。
さまざまな調理にご利用下さい。
キッズ・キッチンとキッズイベントのご予約・お問い合わせ
現在ご予約は、お電話でのみお申し込みを受け付けております。 御食国若狭おばま食文化館 TEL:0770ー53ー1000 FAX:0770ー53ー1036
若狭工房

 若狭おばまの伝統工芸(若狭塗・若狭めのう細工・若狭和紙・若狭瓦)は食の歴史や文化を支えてきました。ここでは伝統工芸を受け継ぐ匠たちが製作した工芸品の販売や、箸研ぎや紙漉きなどの体験を通じて伝統に触れることができます。
若狭おばまの伝統工芸(若狭塗・若狭めのう細工・若狭和紙・若狭瓦)は食の歴史や文化を支えてきました。ここでは伝統工芸を受け継ぐ匠たちが製作した工芸品の販売や、箸研ぎや紙漉きなどの体験を通じて伝統に触れることができます。 | 開館日時 | 9:00〜18:00(3/1〜10/31) 9:00〜17:00(11/1〜2/末) |
| 休館日 | 水曜日(祝日の場合は開館します) 年末年始(12/28〜1/5) |
| 受付時間 | 9:00〜17:00(3/1〜10/31) 9:00〜16:00(11/1〜2/末) |
若狭塗
≪若狭塗の由来≫
 慶長年間(1596〜1614)、小浜の豪商組屋六郎左エ衛門が国外より入手した漆塗盆を藩主酒井忠勝公に献上し、城下の漆塗御用職人松浦三十郎がこれを模して製作したことに始まり、これに改良工夫を重ねて海底の模様を意匠化して菊塵塗を案出、その門人が海辺の貝殻と白砂の美しい景観を表現した磯草塗を創り、万治年間(1658〜1660)に、卵殻金銀箔塗押の技法を完成、藩主酒井忠勝公が「若狭塗」と命名して、小浜藩の藩財政の基幹産業として生産を奨励し、保護しました。
慶長年間(1596〜1614)、小浜の豪商組屋六郎左エ衛門が国外より入手した漆塗盆を藩主酒井忠勝公に献上し、城下の漆塗御用職人松浦三十郎がこれを模して製作したことに始まり、これに改良工夫を重ねて海底の模様を意匠化して菊塵塗を案出、その門人が海辺の貝殻と白砂の美しい景観を表現した磯草塗を創り、万治年間(1658〜1660)に、卵殻金銀箔塗押の技法を完成、藩主酒井忠勝公が「若狭塗」と命名して、小浜藩の藩財政の基幹産業として生産を奨励し、保護しました。
このように、歴代藩主の厚い保護に支えられ多くの名工が輩出して菊水塩干などの優美な意匠が生まれました。
万延元年(1860)には、皇女和宮のご降嫁に際して若狭塗のたんすが献上されたと伝えられ、明治に至り廃藩置県後も、若狭の特産品として奨励され最盛期には器物を製造する業者は40軒、従業員数は70人を数えました。
戦後は資材不足や経済的余裕のない消費者の購買力がなく、商品が売れないため、離職、転廃業が相次いで起こり、現在は7軒、27従業者になりました。
昭和30年以降、高度経済成長とともに産地も落ち着き、根強い需要者の購買力に支えられ、小浜市の特産品として脚光を浴びはじめ、昭和53年2月6日に通商産業大臣より伝統的工芸品の指定を受けました。
また、平成19年10月から放映されたNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」において、主人公の祖父や父が若狭塗箸職人として描かれ、一層の注目を集めています。
 慶長年間(1596〜1614)、小浜の豪商組屋六郎左エ衛門が国外より入手した漆塗盆を藩主酒井忠勝公に献上し、城下の漆塗御用職人松浦三十郎がこれを模して製作したことに始まり、これに改良工夫を重ねて海底の模様を意匠化して菊塵塗を案出、その門人が海辺の貝殻と白砂の美しい景観を表現した磯草塗を創り、万治年間(1658〜1660)に、卵殻金銀箔塗押の技法を完成、藩主酒井忠勝公が「若狭塗」と命名して、小浜藩の藩財政の基幹産業として生産を奨励し、保護しました。
慶長年間(1596〜1614)、小浜の豪商組屋六郎左エ衛門が国外より入手した漆塗盆を藩主酒井忠勝公に献上し、城下の漆塗御用職人松浦三十郎がこれを模して製作したことに始まり、これに改良工夫を重ねて海底の模様を意匠化して菊塵塗を案出、その門人が海辺の貝殻と白砂の美しい景観を表現した磯草塗を創り、万治年間(1658〜1660)に、卵殻金銀箔塗押の技法を完成、藩主酒井忠勝公が「若狭塗」と命名して、小浜藩の藩財政の基幹産業として生産を奨励し、保護しました。
このように、歴代藩主の厚い保護に支えられ多くの名工が輩出して菊水塩干などの優美な意匠が生まれました。
万延元年(1860)には、皇女和宮のご降嫁に際して若狭塗のたんすが献上されたと伝えられ、明治に至り廃藩置県後も、若狭の特産品として奨励され最盛期には器物を製造する業者は40軒、従業員数は70人を数えました。
戦後は資材不足や経済的余裕のない消費者の購買力がなく、商品が売れないため、離職、転廃業が相次いで起こり、現在は7軒、27従業者になりました。
昭和30年以降、高度経済成長とともに産地も落ち着き、根強い需要者の購買力に支えられ、小浜市の特産品として脚光を浴びはじめ、昭和53年2月6日に通商産業大臣より伝統的工芸品の指定を受けました。
また、平成19年10月から放映されたNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」において、主人公の祖父や父が若狭塗箸職人として描かれ、一層の注目を集めています。
≪若狭塗の特徴≫
全国に数多い漆器産地の中でも、「若狭塗」は漆を幾重にも塗り重ねては研ぐという、“研ぎ出し”技法を用いています。極上漆を十数回塗り、貝殻・卵殻・金箔で模様をつけ、石や炭で研ぎ出し、数か月程を要して作られる若狭塗は、独特の重厚感と風格を持ち、愛蔵家指向の家具、什器として幅広く使われています。
若狭めのう細工
≪若狭めのう細工の由来≫
 享保年間(1716〜1735)、当地の高山吉兵衛という人が浪花に出て、眼鏡屋に奉公中丸王製造の技を習得し、帰郷後この事業を始めたのが若狭めのう細工の始まりであると言い伝えられています。
享保年間(1716〜1735)、当地の高山吉兵衛という人が浪花に出て、眼鏡屋に奉公中丸王製造の技を習得し、帰郷後この事業を始めたのが若狭めのう細工の始まりであると言い伝えられています。
その後、明治初年に至り、中川清助が更に技術の改良に苦心し、玉造りに飽き足らず種々の工芸彫刻法を案出し、併せて販路の開拓を図り、内外各地の美術博覧会に出陳して広くめのう工芸の妙を紹介、その都度褒賞の栄に浴し、若狭めのうの名声は徐々に高まり、国内はもとより遠く海外にまで好評を博するに至りました。
明治38年、北海道にその原石を求め、これを共同採掘することを機として、以来業者一致団結して技術の改良、デザインの研究を積み重ねてきました。
戦後、北海道の原石の枯渇や、物品税の導入等により産地の先行きに不安が生じ、約300名程いた従業者の離職が相次ぎましたが、昭和51年6月2日に通商産業大臣より伝統的工芸品の指定を受け、現在では数名の従事者が伝統に一層の磨きをかけて、仏像・唐美人、各種動物類の置物をはじめ、香炉、花瓶、灰皿やブローチ、イヤリング、ペンダント、指輪、ネックレス等の作品を入念に製作しています。
 享保年間(1716〜1735)、当地の高山吉兵衛という人が浪花に出て、眼鏡屋に奉公中丸王製造の技を習得し、帰郷後この事業を始めたのが若狭めのう細工の始まりであると言い伝えられています。
享保年間(1716〜1735)、当地の高山吉兵衛という人が浪花に出て、眼鏡屋に奉公中丸王製造の技を習得し、帰郷後この事業を始めたのが若狭めのう細工の始まりであると言い伝えられています。その後、明治初年に至り、中川清助が更に技術の改良に苦心し、玉造りに飽き足らず種々の工芸彫刻法を案出し、併せて販路の開拓を図り、内外各地の美術博覧会に出陳して広くめのう工芸の妙を紹介、その都度褒賞の栄に浴し、若狭めのうの名声は徐々に高まり、国内はもとより遠く海外にまで好評を博するに至りました。
明治38年、北海道にその原石を求め、これを共同採掘することを機として、以来業者一致団結して技術の改良、デザインの研究を積み重ねてきました。
戦後、北海道の原石の枯渇や、物品税の導入等により産地の先行きに不安が生じ、約300名程いた従業者の離職が相次ぎましたが、昭和51年6月2日に通商産業大臣より伝統的工芸品の指定を受け、現在では数名の従事者が伝統に一層の磨きをかけて、仏像・唐美人、各種動物類の置物をはじめ、香炉、花瓶、灰皿やブローチ、イヤリング、ペンダント、指輪、ネックレス等の作品を入念に製作しています。
≪若狭めのう細工の特徴≫
「若狭めのう細工」は、わが国の貴石細工のルーツです。「めのう」は古くから七宝の一つに数えられ、優雅で艶麗な色調は人々の心を魅了すると言われています。
硬い石を砕き、思いのままの作品を彫刻する技法は、寸時の油断も許されない厳しい修行のなかから生まれ、独特の技術を駆使して彫刻される「若狭めのう細工」は、宝石工芸の最高峰といっても過言ではありません。
若狭和紙
≪若狭和紙の由来≫
 和紙の歴史は古く、延暦(782〜806)の頃、田村の地(現在の小浜市和多田地区)は、昔坂上田村麻呂の荘園で、その家来大膳大夫高階行宗が支配していました。その頃に和紙の製造技術が伝わったものと言われています。
和紙の歴史は古く、延暦(782〜806)の頃、田村の地(現在の小浜市和多田地区)は、昔坂上田村麻呂の荘園で、その家来大膳大夫高階行宗が支配していました。その頃に和紙の製造技術が伝わったものと言われています。
書物には、『若狭国志』の田賦貢輪の中で「守中男作物ノ紙」の記述があり、延喜(901〜922)の頃、若狭から都へ庸として紙が送られていたことが記述されています。また、『若狭郡県志』によると、現在の小浜市湯岡、和多田、おおい町名田庄三重などで漉かれていたと記録されています。
小浜藩主酒井忠勝公の治世に、コウゾ、ミツマタの栽培を奨励したことによって製造が盛んになったと伝えられ、家内手工業として発達してきました。明治初期の社会転換期の影響を受け、今では和多田地区で数戸だけが伝統の紙漉きの技術を受け継いでいます。
 和紙の歴史は古く、延暦(782〜806)の頃、田村の地(現在の小浜市和多田地区)は、昔坂上田村麻呂の荘園で、その家来大膳大夫高階行宗が支配していました。その頃に和紙の製造技術が伝わったものと言われています。
和紙の歴史は古く、延暦(782〜806)の頃、田村の地(現在の小浜市和多田地区)は、昔坂上田村麻呂の荘園で、その家来大膳大夫高階行宗が支配していました。その頃に和紙の製造技術が伝わったものと言われています。書物には、『若狭国志』の田賦貢輪の中で「守中男作物ノ紙」の記述があり、延喜(901〜922)の頃、若狭から都へ庸として紙が送られていたことが記述されています。また、『若狭郡県志』によると、現在の小浜市湯岡、和多田、おおい町名田庄三重などで漉かれていたと記録されています。
小浜藩主酒井忠勝公の治世に、コウゾ、ミツマタの栽培を奨励したことによって製造が盛んになったと伝えられ、家内手工業として発達してきました。明治初期の社会転換期の影響を受け、今では和多田地区で数戸だけが伝統の紙漉きの技術を受け継いでいます。
≪若狭和紙の特徴≫
水のきれいな若狭小浜で育まれた「若狭和紙」は、精選されたコウゾを原料とした純良で頑丈な和紙です。
かつては、絹布などの包紙として愛用され、和傘、障子紙、研磨紙、襖紙なども生産していました。現在は、美工紙も手掛け、名刺やアドレス帳、和紙人形の材料として使われています。
濱の湯
 濱の湯は、医食同源の観点から、心身の疲れを癒し、リラックスできる温浴施設としてオープンしました。オーシャンビューの施設で海草風呂、薬草風呂、サウナ、マッサージを堪能することができます。また、マリンデッキでは足湯(無料)が楽しめます。
濱の湯は、医食同源の観点から、心身の疲れを癒し、リラックスできる温浴施設としてオープンしました。オーシャンビューの施設で海草風呂、薬草風呂、サウナ、マッサージを堪能することができます。また、マリンデッキでは足湯(無料)が楽しめます。
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 休館日 | 毎月第3水曜日、メンテナンス日(不定期) ※足湯は冬季間(12月〜4月上旬)閉鎖いたします。 |
| 料 金 | 大人(中学生以上)650円 小人(小学生以下)320円 ※3歳未満は無料 市内の高齢者(70歳以上)、市内の障がい者540円 回数券(11枚綴)6,500円 |
濱の四季
 濱の四季は、水産物供給施設として建設。地場産の食材にこだわり、伝統料理を中心に提供しています。スタッフは地元の女性グループで構成されており、御食国若狭おばまのスローフードをお楽しみいただけます。
濱の四季は、水産物供給施設として建設。地場産の食材にこだわり、伝統料理を中心に提供しています。スタッフは地元の女性グループで構成されており、御食国若狭おばまのスローフードをお楽しみいただけます。