※画像クリックで拡大写真
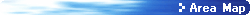
|
 指 定 指 定 |
 所在地 所在地 |
 管理者 管理者 |
|
| 平成14.4.23 県指定 |
小浜市男山 |
小浜地区(24区) |
|
放生とは捕らえられた魚鳥に法を修して山野、池水に放つ慈悲行で、この法会を放生会という、わが国では天武天皇5年(677)8月、諸国に詔しての放生を初見とし、社寺では養老4年(720)の宇佐八幡宮放生会を始めとし、八幡宮では独自の法会として発展した。
後瀬山麓鎮座の八幡神社は地方の大祀で、鎌倉時代には鎮守大明神に列し若狭一の宮に次ぐ崇敬をうけた社である。当社中世の放生会には管弦、流鏑馬が、近世には神事能、管弦、相撲などが奉納されている。
毎年9月14、15日(平成16年度から9月の第3土日)の例大祭(放生の儀礼はないが、古来より放生会という)に奉納する出し物は、寛永15年(1638)以降、市内千種に鎮まる広嶺神社の祗園御霊会(祗園祭礼絵巻)に際し、当社の御旅所に滞在される祗園三神輿の還幸に伴って奉納される。往時は各町内毎に笠鉾、棒振り、大太鼓、神楽、花車、曳山や数寄を凝らした仮装の行列などを繰り出し、巡行に華麗な風流を競演していた。しかし明治維新後はすべて当社放生会に奉納の出し物となり、さらに明治7年(1874)の町区改編を契機として内容的にも大幅な変改を余儀なくされ、近年では大太鼓5区、山車9区、獅子舞(雲浜獅子、内容は同じ)4区、神楽5区、神輿1区の計24区に固定化し、交互隔年に12区づつ出陣して賑やかな祭囃子のなか、当社社頭及び各区の本陣等を巡行し伝統の神事芸能を演舞奉納している。『稚狭考』はかつての祗園会巡行を評して、敦賀、長浜、大津の祭りにはじぬ風流と記しているが、いまも豪華絢爛を極める若狭路最大の秋祭りとされている。
|