
※画像クリックで拡大写真
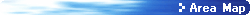
|
 指 定 指 定 |
 所在地 所在地 |
 管理者 管理者 |
|
| 昭和57.4.20 市指定 |
小浜市大手町 |
小浜市 |
|
組屋家は近世小浜町人筆頭の豪商である。豊臣氏以降浅野、京極、酒井家に仕え領主と組み豪商の地位を固め廻船、貿易の業者として目覚しい活躍をした旧家で、組屋文書の一部は早くから世に知られて著名である。
組屋家は浅野長政の若狭領知の時代、既に門閥的町人となっている。文禄元年(1592)秀吉の朝鮮出撃に先立ち、長政の命を受け、兵糧の米や大豆を九州名護屋へ輸送する業務に携った。写真に掲載した文書は、秀吉の右筆山中橘内(山城守長俊)が秀吉のアジア支配構想とでもいうべきものを大阪城留守居の秀吉の侍女に宛てた有名な書状である。また、豊臣恩顧の諸大名に当時の珍重品ルソン壺類を売捌いたり、津軽で徴収した大量の豊臣氏上納米を南部や小浜へ運んだ事実が窺われる。
慶長5年(1600)京極高次の若狭支配が始まると組屋はその代官となり、遠敷・大飯両郡内諸所の支配を司った。また小浜町中の商人から公用米(あるいは銭)を徴収する特権を安堵されている。
酒井忠勝入部の際も京極氏と同様、国主の宿を勤め、公用銭徴収権も代々安堵され、諸公事も免ぜられた。宝暦10、11年(1760、61)小浜藩士らが扶持米を抵当に藩の蔵米を借用した際の証文類もある。安政元年(1854)4月御所内の失火に端を発した京都の大火の模様、また明治維新政府の貨幣政策に関係するもの、旧記抜書は幕末の小浜における大小の諸事件や商取引に関する記録で興味深い。これらの古文書によって小浜の町政、商業、港などの様子が知られるのみならず日本史としても貴重な資料である。
|