
※画像クリックで拡大写真
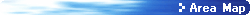
|
 指 定 指 定 |
 所在地 所在地 |
 管理者 管理者 |
|
| 大正13.4.15 国指定 |
小浜市神宮寺 |
天台宗神宮寺 |
|
この寺は奈良朝初期元明天皇和銅7年(714)泰澄大師の弟子滑元が創め、その翌年勅願所となり神願寺と称し、やがて白石鵜の瀬より、遠敷明神を勧請したゆかりの地と伝えられている。
平安時代に桓武天皇、白河天皇の勅命により伽藍が再建されたといい、鎌倉時代には将軍頼経は七堂伽藍二十五坊を寄進し、若狭一の宮の別当寺となるに及び、寺号を根本神宮寺と改めた。室町初期に細川清氏の再興あり、現本堂は天文22年(1553)越前守護朝倉義景が再興したものである。しかし今は仁王門、本堂、開山堂、円蔵坊、桜本坊を遺すのみであるが、本堂は昭和30年解体修理を終えて今の偉容をみるのである。
本堂は五間六間の建物である。すなわち桁行五間、梁間六間であって、間口14.34m、奥行16.60mの単層入母屋造、桧皮葺で、石基壇上に立ち、腰四面に廻縁を設け勾欄を巡らしている。
太い円柱に和様出組の斗栱を用い、蛇腹支輪を備え、中備には正面に精巧な本蟇股を置き、正面五間ともに折上蔀戸を建て、二軒繁棰をもって覆いたる本堂は、中世末期建築として実に堂々たる風姿で君臨するかのようである。和様を主体とするけれども、各所に大陸の様式を取り入れ、木鼻に天竺様繰形を用い、内部の束梁ともに唐様手法多く、妻飾も軒隅の反転とともに華麗な姿を一層かき立てているようである。
|